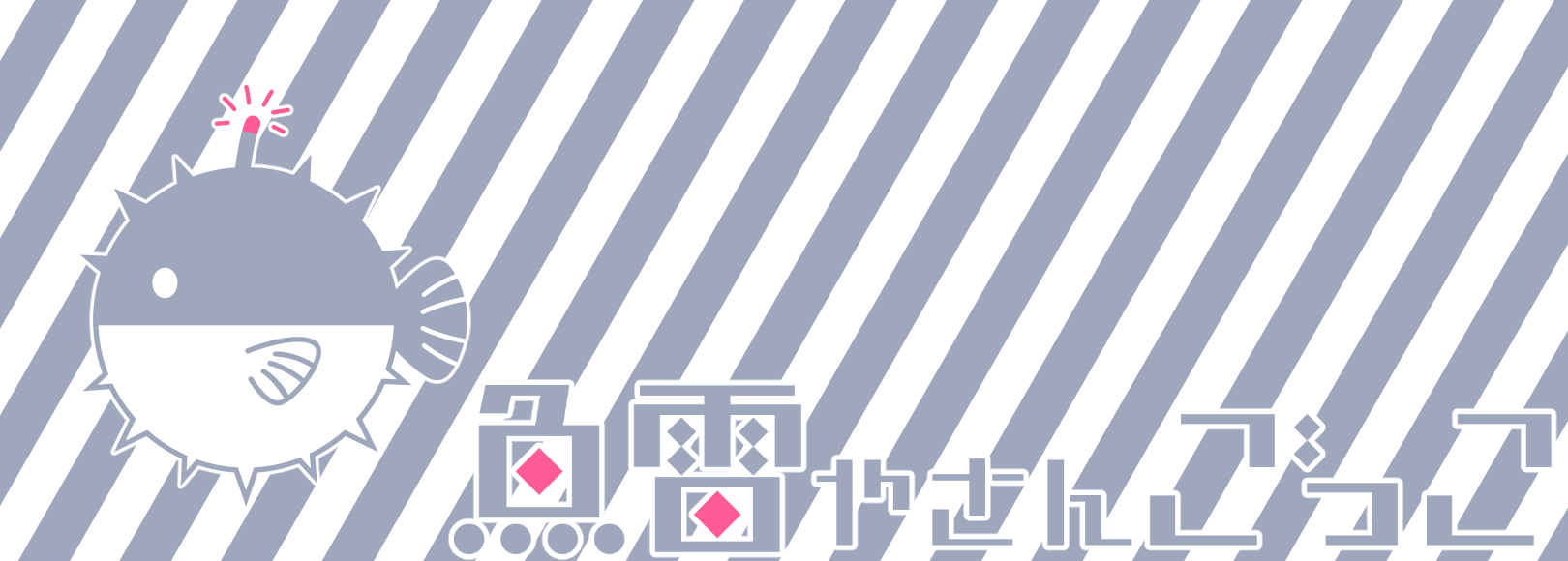フランチャイズのファストフード店。その一角に優と千種川はいた。二人は一袋のフライドポテトをつまんでいた。
おもむろに千種川が口を開く。彼の口から、彼に似合わない単語が出てきたことに、優は手元のフライドポテトから視線を上げる。
「先日はエイプリルフールでしたね」
「あー、そうだったわね。なんか、春休みで引きこもってたから、そんな日もあったなー程度の認識だわ。別にSNSをいつも見てるわけでもないし」
「企業のツイッターアカウントなどでは、エイプリルフールに乗じたユニークな投稿がなされていたようですね。姉が言ってました」
「あんたのお姉さん、会ったことあんまりないけど、そういうのよく見る人だっけ?」
「ええ、母からSNS中毒と呼ばれる程度には。リビングに滞在中、スマートフォンを操作している時間は、ほぼ全ての時間ですね。食事の時も手放そうとしないので、よく叱られています」
呆れたものですよね。千種川は口を開く。フライドポテトをつまむ彼にさほど興味もなさそうに、優はお姉さんスマホ繋がらなくなったら目の前が真っ暗になりそう、と笑う。
その比喩表現に、千種川は不思議そうに首を傾げる。それに気がついた優は、ゲームにそういう表現があんのよ、と続ける。
「ポケモンだっけ? 手持ちの仲間が全滅して戦えなくなると、目の前が真っ暗になったー、ってアナウンスが入るのよ」
「なるほど。たしかに前の体の持ち主の記憶にありますね、その情報は。彼も遊んでいたのでしょうね」
「世界的な人気タイトルだしね、遊んでたんじゃない? あたしも家にあるし」
あれ、図鑑埋めるの一人だとできないから、よく姉さんに頼まれたわ。
からからと笑いながら、優はジュースに口をつける。炭酸が少しばかり抜けたそれは、ずいぶん甘ったるく喉を潤す。
姉さんは最新作のもやってるけど、あたしは興味ないな。そう言った優に、そうなんですね、と千種川は返す。
「どうにもねー。なんかそこまでゲーム自体が好きじゃないんだよね。時間潰すのにはいいんだけど、クリアするまでやる気が持たないっていうか」
「なるほど。そういうものかもしれませんね」
「まあ、人によるんだろうけどさ。それこそ、一日中プレイしてストーリークリアして、やり込み要素やったりさ」
「そうですね。好きな人なら、タイムアタックの動画を投稿サイトにアップロードする人もいますしね」
「……あ、そういや、そういう人ってあんたの母星にもいるの?」
YouTuberみたいな人、と続ける優の言葉に、千種川は何かを思い出すように軽く目を伏せる。そうですね、と溢してから、いましたね、と千種川は続ける。
その言葉に、優はやっぱりゲームとか歌ったりするの、と興味深そうに尋ねる。そういう放送もありましたね、と言った彼は、あまり僕は見ていませんでしたが、と続ける。
「本の感想や朗読などもありましたね。プロ、アマチュアの作家問わず行う人も」
「へえ。新しい本探すのに便利そうだね、そういう人の配信」
「母星の友人もそう言っていましたね。あいにく、僕は他人に勧められた本を買うより、自分で探すほうがすきでしたから、その手の配信は見ていないですが」
「あんた、そういう手合いだなって思ってるから、見てたら逆に驚くよ」
けらけら笑った優は、最後の一本のフライドポテトをつまみ上げる。咀嚼している彼女は、空になったジュースの紙カップをトレイの上に置く。千種川はトレイを持ち上げて、ダストボックスにゴミを捨てると、ボックスの上にトレイを戻す。
優が荷物を持って立ち上がると、千種川はこの後は服を見ますか、と尋ねてくる。二人連れ添って店を後にしながら、優はアクセサリーも見たいかな、と返す。
「この間、ヘアアクセサリーが壊れちゃってさ。バンスクリップなんだけど」
「なるほど。それで新しいものが必要だと」
「めちゃくちゃ欲しい、ってわけでもないけど、あるにこしたことはないからね」
「そういうことでしたか。アクセサリーショップは二つ上の階でしたね」
「おしゃれなやつがあればいいんだけどね」
そう話しながら、二人はエスカレーターに乗る。優の人目を惹きつける肢体に、彼女の後ろに立った男性は、居心地悪そうにそれとなく視線を逸らしていた。