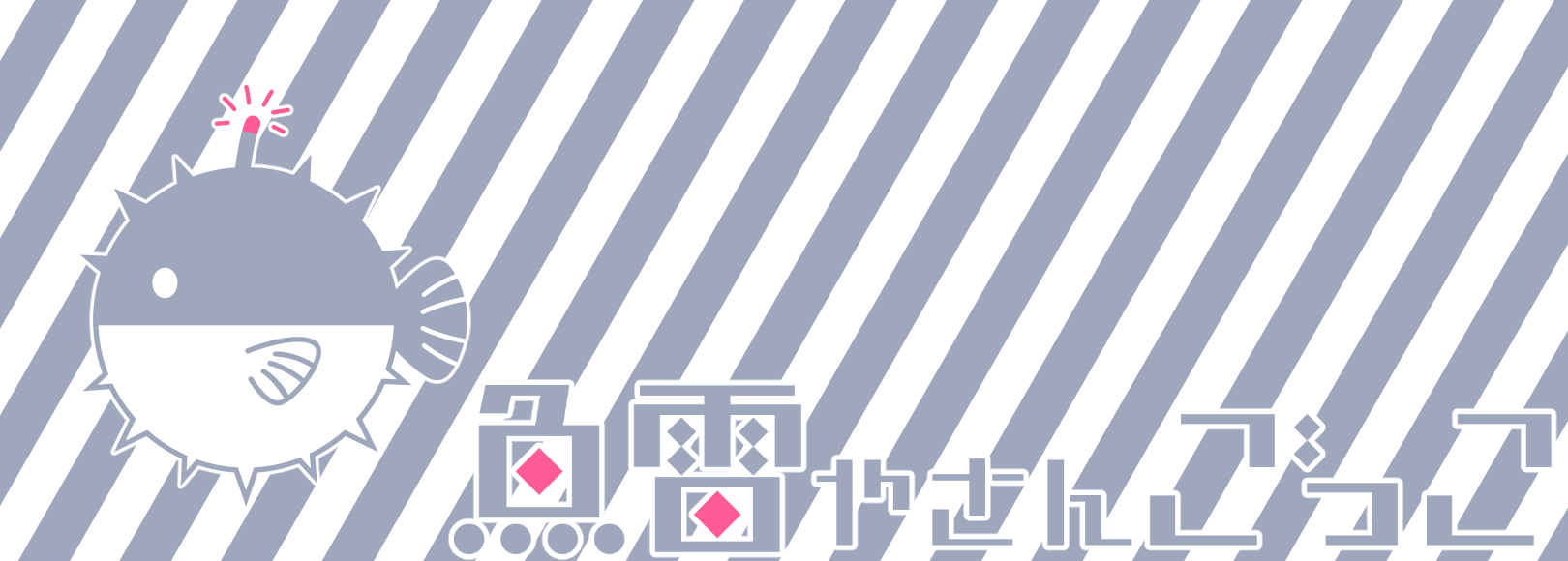「先日読んだマンガにあったのですが」
「ん?」
「焼いたマシュマロが美味である、とありましたが事実なのでしょうか」
「あー……まあ、たしかに美味しいかな」
あたしはあんまり焼いたことないけど。そう言いながら優は、最後に焼いたのは、たしか小学校の林間学校だっただろうか、と思い出す。あのときだって、カレーを作ったときの余った火で焼いたはずだ。あれはおいしかった……ように思う。
何年も前の記憶を呼び出しながら、そんなことを考えていると、そうなのですね、と千種川は顎を撫でる。今ひとつ理解していないようだったから、そんなに気になるなら実際に試してみたらどうだ、と優は提案する。いつだってこの男は、少しでも気になることがあれば実際に行動していた。それを促しただけだ。実際、千種川はそれはそうですね、と頷く。
それで終わるだけの話だった。少なくとも、優の中ではそれで終わったのだった。強いて言えば、優もマシュマロが食べたくなったから、近くのスーパーで小さな袋に入ったマシュマロを買ったのだけれど。それだけだった。
そんなやりとりをしてから、数日が経った。
優は数学の宿題を片付けたから、翌日の授業の準備をしていたときだった。スマートフォンが振動したものだから、どうせダイレクトメールだろうとあたりをつけてから、優はスクールバックから離れて、机に手を伸ばしてスマートフォンを手に取る。
画面に写っていたのはメッセージアプリの新着メッセージの通知だった。送信主は千種川だった。
彼からメッセージが来るのは珍しいわけではないが、写真だけが送られてくるのは早々なかった。いつもはテキストメッセージが主で、写真が送られてくるのは珍しかった。店舗にいくときの資料はだいたいがウェブサイトのアドレスが添付されていた。
はて、と思いながらメッセージを開くと、そこにあったのは焦げ目の付いたマシュマロだった。よく焦げた――表面が炭化しかけているものもあれば、わずかに焦げ目がついた程度のものまで様々だ。大方、何種類かのパターンにして甘さの変わり方を研究しているつもりなのだろう――そう優は当たりをつける。
「焼き方変えた程度じゃ、甘さなんて変わらないでしょうに」
そうつぶやきながらメッセージを開くと、次に黒く表面が炭化したマシュマロの写真が送られてくる。それについで送られてきたテキストメッセージには、炭化した表面の影響で苦みがある、と書かれていたものだから、優はそりゃそうだろうよ、とふは、と息を漏らして笑う。
そこからは写真とテキストメッセージが一方的に送られてくるだけだった。優はひとつずつ返信するか少し悩んだが、もう面倒くさくて最後にまとめて返信して、それまでは既読をつけるだけにしておこうと思った。
軽く焦げ目がついたものは苦みが少ない、という当たり前のコメントがついたりしながら、優はスマートフォンを机の上においたまま、放置していたスクールバックに教科書を詰め込み直す。教科書とノート、筆箱、参考書をカバンに詰める。
じーっ、とファスナーをしめて準備を終えてから、優は放置していたスマートフォンを手に取る。知らない間にメッセージがそれなりの数たまっている。それぞれの写真とテキストをスクロールしながら見る。最終的な結論として、一定量焼いてしまうと舌で感じられる甘さは変わらない、と書かれているものだから、そうでしょうよ、とまた口にしてしまう。むしろ、焼きすぎれば黒く炭化するものだから、逆に苦くなるだろう。
そういえば、マシュマロって何で出来てるんだっけか、と思いながら、優はメッセージアプリの入力欄をタップする。あれって焼いて甘くなるってことは最初から甘いんだっけ、と入力する。ふわふわとしているばかりで、口に入れたときに強烈な甘さをあまり優は感じないのだ。むしろ、なにかに覆われているような、中途半端な甘さを覚えるのだ。独特の弾力がそう思わせているだけなのかもしれないが。
すぐに千種川からの返信が戻ってくる。砂糖、卵白、ゼラチン、水飴が原料なので甘いです、と。弾力があるから甘さを君が感じにくいのかもしれませんね、とも。
そう書かれて優は、たしかに溶けたマシュマロは甘ったるい、と合点がいく。原材料を見てから、親が外国の大型スーパーマーケットで買ってくるマシュマロ入りのココアを思い返す。あれはマシュマロを口にしなくても相当甘いと思うが、一包に含まれる全てのマシュマロを溶かしてしまったらどれだけ甘ったるくなるのだろうか、と想像してから、あたしじゃ飲めないわね、と優はメッセージアプリに返信を打ち込むことにした。