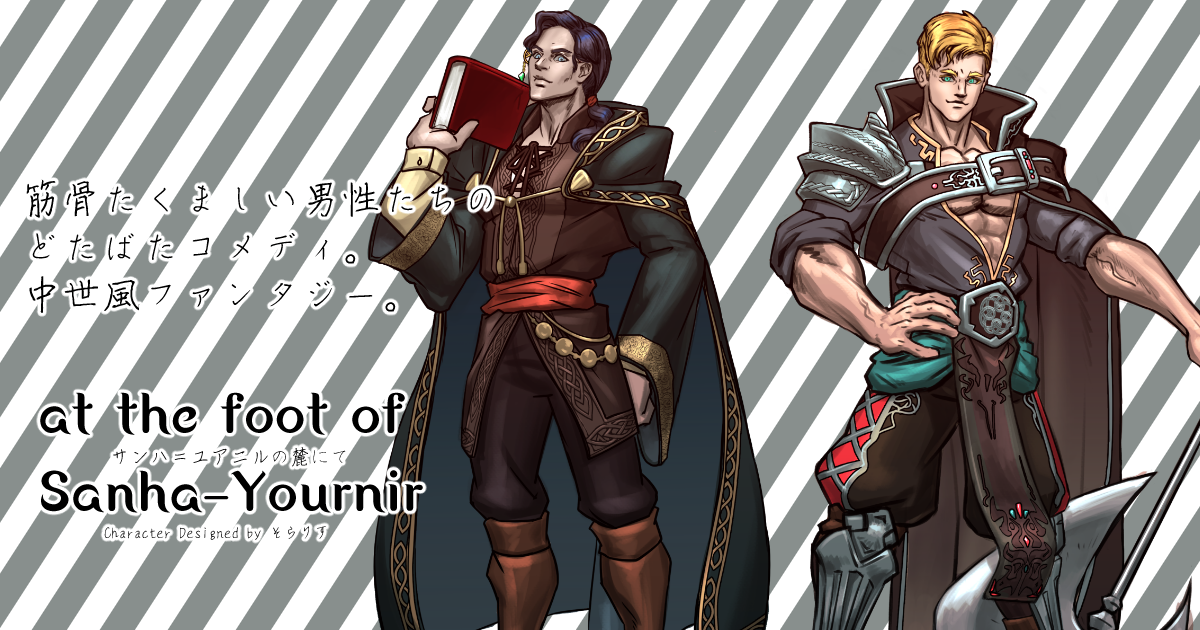黄金鶏のハムを挟んだ黄金鶏の食パンを使ったサンドイッチを手に、マクシミリアンはサンハ=ユアニルの街を歩いていた。
街はお祭り一色で、大通りは多くの露店で賑わっているし、飲食店の店先にあるテラス席はアルコールに酔った人々が歌ったりしている。街の中心にある広場では、領主お抱えの楽団が音楽を奏で、人々がめいめい好き勝手に踊っている。
年に一度の収穫を祝う祭りであるから、人々も盛り上がっている。この祭りが終われば、サンク・キタテウェルトで最も早く冬が来るのだ。だからこそ、人々は冬が来る前に最後の秋を楽しむのだ。
猟師仲間たちと飲んで騒いでの大騒ぎ中のヴォルフガングをよそに、マクシミリアンはサンドイッチとホットワインを手に、喧騒の中心から離れたところにある井戸と、その横に備え付けられた歓談用のベンチに腰を下ろした。
分厚いハムとこれがこの季節最後になるだろう生のトマトを噛みちぎる。塩っぽさの強いハムごとサンドイッチを飲み込み、ホットワインを口にする。夜に差し掛かり、気温が下がり、冷えた体にちょうどいい味だ。
マクシミリアンがのんびり飲食を楽しんでいると、一人の少女がやってくる。もみくちゃにされたのか、長い黒髪はあっちこっちに跳ねていて、顔も覆い隠してしまっている。乱れた髪を直しながら歩いてくる彼女は、少し前に異世界から引っ越してきた少女、鈴だ。
人の気配にぎょっとしていた彼女だが、そこにいたのがマクシミリアンだと理解すると、安心したようにベンチに近寄ってくる。座りやすいようにベンチの端に移動したマクシミリアン(それでもベンチの半分近くを埋めている)に、鈴は頭をぺこりと下げて、反対側の端に座る。
「えらいもみくちゃにされてるな。頭が鳥の巣になってるぞ」
「ま、前に、その、絵本書いたってのが、その、知れ渡ってたみたいで……」
「はは。ここのやつらは悪気はないんだが、狭い街なもんだから、あっという間に噂が広がるからな。街の噂になっていたしな、おもしろい絵本だって」
「そ、そうなんです、か……!? わ、わたしの絵本、前の世界の、その、好きな作品を元にしたものだから……」
おろおろしている鈴に、マクシミリアンは笑う。絵が得意だと圭太に聞いたマクシミリアンが、彼女に短い絵本を作らせてみたのだ。
まだこちらの統一言語が書けない彼女に代わり、マクシミリアンが彼女の物語を書き起こし、鈴が可愛らしい絵を添えていく。そうしてできた、腹を空かせた可愛らしいドルノとラギウスが食事を作る絵本は、サンハ=ユアニルの街で話題の本となったのだ。
柔らかい色合いの絵と、可愛らしい話は子どもに読み聞かせたいと図書館でひっきりなしに借りられている。大枚叩いて買う人もいるほどだ。
「こっちじゃ子ども向けの絵本がまず高くてな。製本に金がかかるから、どうしても子どもよりも専門知識のものが優先されやすい。なんせ金を払ってでも手に入れたいっていう知識人ばかりだからな」
「そ、そうらしい、です、ね。メイナードさんも、図書館の人も、言ってました」
「そんな本ばかりが売れてるっていうのに、絵の書いてある本を子どもにも見せたいって金持ちがこぞって買うときた。そりゃあ、絵の具代どころか紙代もあっという間に稼げて驚いたよ。知り合いの編集も喜んでいたよ。続編も書いて欲しいとよ」
「そ、そうなんですか……!?」
大仰に驚く彼女に、マクシミリアンは認められてるんだよ、と快活に笑う。続編なんてすぐに思いつかない、と顔を覆う彼女に、思いついた時に書くのが一番だ、とマクシミリアンは顎をさする。自分の作品が認められるのははじめてだ、とぼそりと呟いた彼女に、認められるのはいいことばかりじゃないがな、とマクシミリアンは肩をすくめる。
「悪口雑言がしらんやつらから送られてくるところも見たことがある。ま、そういうのは気にしないのが一番なんだが……お前さんじゃ気にするだろうな……」
「ううっ……」
「ま、そういうのから守って貰うために、商業で本を出したんだ。お前さんの住所は……まあ、ここいらの奴ら以外には早々ばれちゃいないだろうから、安心しろよ」
家まで追いかけてくるやつらなんて、早々いないしな。
遠い目をしながらそう話す彼に、鈴はそんな人が居たんですか、と思わずマクシミリアンの方を見る。いたぞ、と事もなげに話してくる彼に、こわ……と鈴はぼそりと呟いてしまう。
「まあ、そもそも俺はドルノと仲が良いから、あいつらの鱗をもらったりしていたしな。だいたい家にまでやってくるのは、そういう滅多に流通しないもの目当てのやつらだよ。まあ、返り討ちにしてやったがな」
「返り討ちにしたんですか……」
「ヴォルフガングのやつがほとんどな」
「ああ……あの人なら……なんとなくわかると、いうか……」
「ろくでもないやつらだったな……憲兵達にしょっぴいてもらったもんだよ」
ま、そんなやつらが早々くることはないから安心しろよ、と笑うマクシミリアンに、鈴はそれもそうですね、とひきつった笑みを浮かべるばかりだった。へへ、と引きつった笑いをする彼女の腹からぐるぐる、と合唱が聞こえてしまったものだから、鈴は顔を赤くしたり、青くしたりと忙しくする。腹が減るのは健康な証拠だな、とマクシミリアンが笑う。
「なにか食いに行くか」
「うう……はい……」
「俺もサンドイッチだけじゃ足りんしな……」
「サンドイッチ食べたんですね……」
「向こうに黄金鶏のハムとトマトのサンドイッチが売られていてな」
「おお……! おいしそう、です」
「うまかったな。ルシアナのパン屋もまだ行ってないし、そっちに行くか」
たしかこっちだったな……と歩いて行くマクシミリアン。置いていかれないよう、やや小走りで追いかける鈴。それに気がついた彼は、いつもよりもゆっくりめに歩いて、彼女の歩調に合わせるのだった。