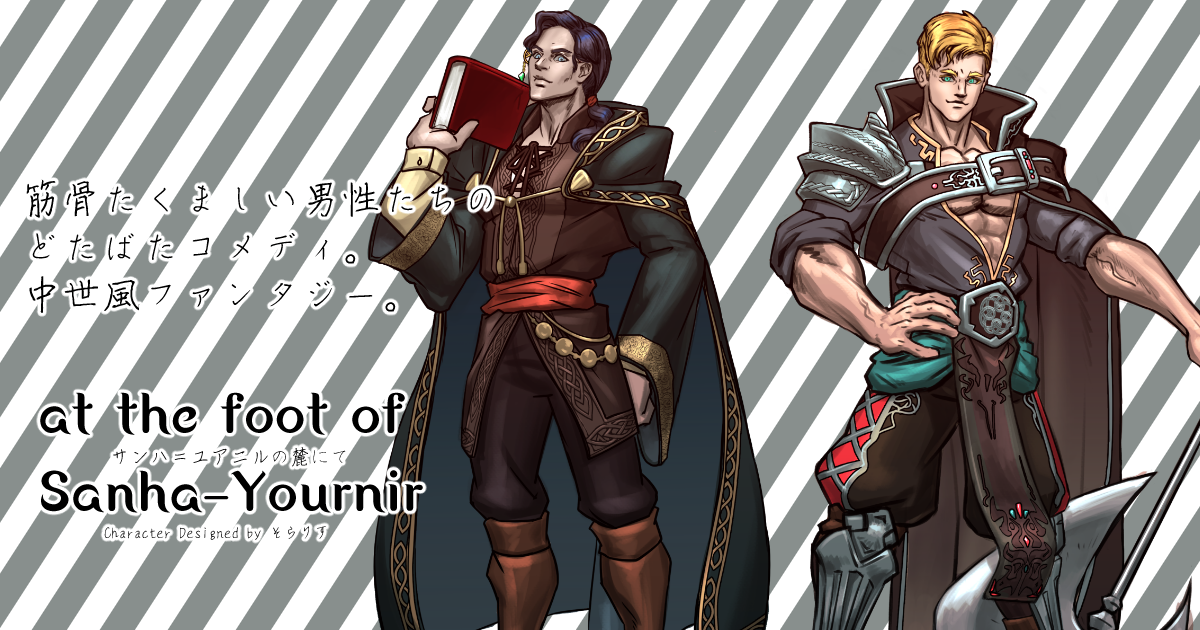新年を迎えたサンハ=ユアニルの山は雪で白く化粧をしていた。麓の街も白く染まっている。人々は思い思いに家の前や、屋根に積もり始めた雪を融雪溝に落としていく。
それは街から離れたところに住むマクシミリアンとヴォルフガングも同じだった。石と木で作られた家が雪の重みで潰れる前に雪をどかすが、もうその作業も日に何度したか分からないほどだ。散歩に連れ出したキーリスは、マクシミリアンとヴォルフガングの膝ほどまで積もった雪に埋もれて、楽しそうに鳴く声と、困ったように鳴く声が雪に反響させるばかりだ。
ラギウスの幼犬を雪の中から拾い上げると、二人は手分けして家の周りの雪をかき出す。その間にも降り積もる雪は積もり続けていくが、あらかた家から退かすことができたのを確認すると、マクシミリアンは腹減ったな、と家に引き返す。それを追いかけてヴォルフガングも家に引き返していく。
「動いたから暑いんだが、外がさみぃな」
「寒暖差が激しいな。年も越したし、どうだ?」
「お、新年らしくていいんじゃねえの」
鮮度を維持する魔法がかけられた新鮮なトトユ牛の肉をマクシミリアンが見せると、ステーキにしようぜ、とヴォルフガングが頷く。分厚く切り分けられたそれをまな板に置いたマクシミリアンは、味付けはいつものでいいよな、と塩と胡椒を振りかける。
「新年早々珍しい味付けで外したくはないよな」
「そりゃそうだ。冒険心ってのは、なんでもねえ日に膨らませてなんぼだよな」
「ヴォルフガングにしちゃあ、随分まともなこと言うな」
「俺にしちゃあ、ってなんだよ。いつだって真面目そのものだろ、失礼だな」
薪を暖炉に焚べながら、ヴォルフガングは唇を尖らせる。雪まみれのキーリスが、燃える薪を興味深そうに見ている。ぶるぶるぶる、と体を震わせて体毛についた丸い雪を吹き飛ばそうとしてみるが、毛にしっかりとくっついた雪はその程度では落ちない。それどころか、暖炉に近づいたこともあって、溶けて床を濡らしていく。
それを見つけたヴォルフガングが、雑巾どこしまったかとマクシミリアンに尋ねる。物置、とフライパンに油を敷いて温めている彼は、ヴォルフガングを見ることなく答える。
雑巾を取りにリビングから出たヴォルフガングは、廊下まで熱が伝わってないために冷え切った石と木の建物の冷たさに、さみい、と声が漏れる。冷えた廊下を歩いて、物置として使っている部屋の扉を押し開ける。
雑多に詰め込まれた物の中から、比較的最近使ったからか手前に置いてあった雑巾を一枚手に取る。扉を閉めて、寒さから体を丸めた彼は、気持ち小走りになってリビングに戻る。
リビングに入れば、暖炉の熱が部屋全体を暖めているために、縮ませていた身体を伸ばす。あったけえな、とぼやきながら、ヴォルフガングはぷるぷると体を震わせて溶けた雪を払っているキーリスの周りを雑巾で拭く。ついでに雑巾をひっくり返して、キーリスの短い琥珀色の体毛を拭いてやると、がうがうきゃんきゃんと嫌がりつつも気分良さそうにラギウスの幼犬は鳴いている。
肉が焼けるいい匂いと音が部屋に広がる。じゅわっと油がはぜて火が肉に通っていく。フライパンを振るいながらマクシミリアンはヴォルフガングに尋ねる。
「肉の付け合わせはどうする」
「肉だけでいいだろ」
「よくねえわ。たまねぎを炒めたやつでいいか……じゃがいもの蒸したやつもいいな……」
「肉だけでいいだろー……」
「よくねえっつってんだろ。今から蒸すと時間がかかりすぎるか……今日はたまねぎでいいか」
ぶつぶつと文句をいうヴォルフガングをよそに、マクシミリアンは保冷魔法のかかったアイスボックスからよく炒めたたまねぎを取り出す。フライパンから肉を下ろして、空いたフライパンで軽く火を通す。その間に、ヴォルフガングは新年の休みに入る前に買い込んだパンをいくつか引っ張り出す。バゲットを何枚かスライスして皿に乗せる。
皿に肉とたまねぎの炒めものを乗せると、マクシミリアンはソースはいらねえだろ、とにっと口角をあげる。そのまま食うのが一番美味いからな、とヴォルフガングも口角を上げる。
キーリス用に切り分けた肉を置いて、マクシミリアンは肉をテーブルに置く。肉とパンと気持ちばかりの野菜に、新年の手抜きだな、と嘆くマクシミリアンに、新年くらい肉単体でもいいんだがな、とヴォルフガングはフォークとナイフで肉を切り分け始めるのだった。