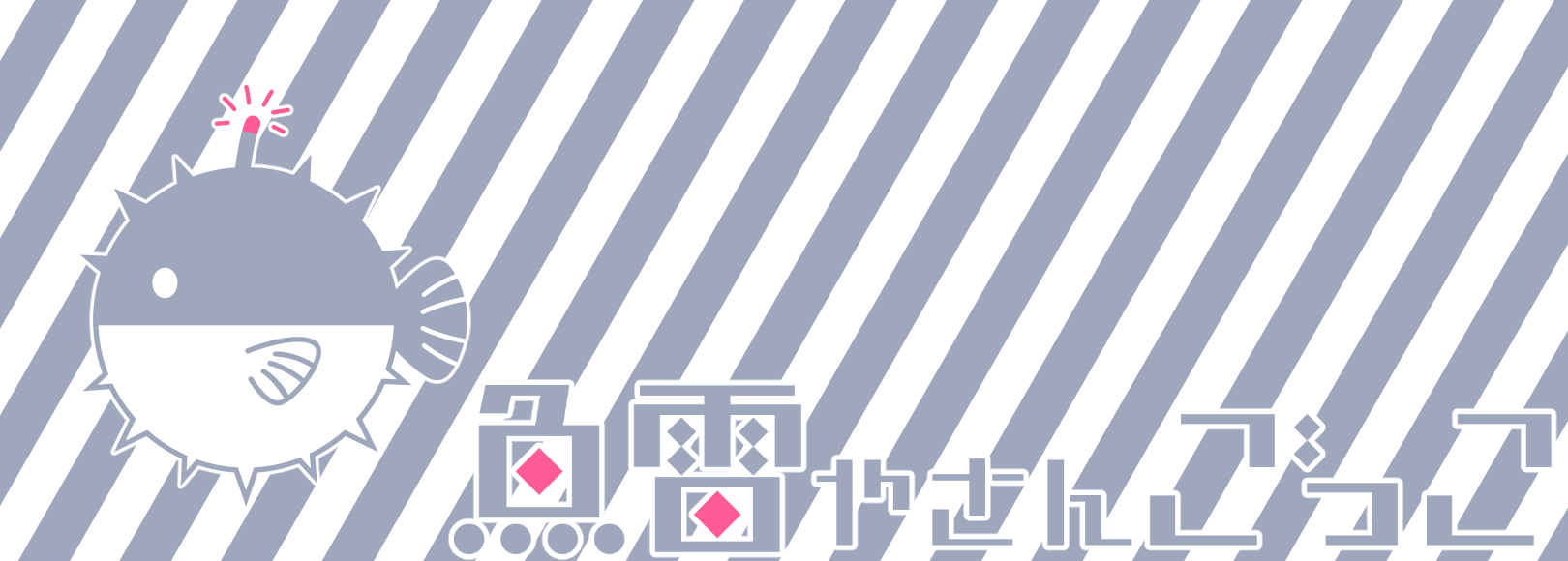汗が吹き出して止まらない。猛暑日だとか酷暑日だとか、とにかくひどい夏の暑さに優は左目を伏せて汗をタオルハンカチで拭う。目に染みる汗は、いくら拭いても止まりそうにない。
隣に立つ男・千種川雅貴もまた、顔の横を流れる汗をガーゼ生地のハンカチで拭いていた。無表情ながら、どことなく暑さを嫌がる顔をしているように見える。
「災害級、とはよく言ったものよね」
「ですね。どうしますか、どこかで休みますか」
「ホテルで昼寝、ってキメたいところだけど、涼しむことができるなら、喫茶店でもマックでもどこでもいいわ……」
「同意です。氷菓の類を摂取したいです」
「珍しいじゃん。あんたが食べたいものを言うなんて」
「それだけ暑い、ということです。どうですか、ここは。ここのかき氷は、たしか、写真写りのものよりも大きいんでしたよね?」
「ん? あ、ああー。ここのは大きいわ。うん」
愛知県が発祥のフランチャイズの喫茶店を見つけた千種川は、掲示されているかき氷を指さして優に問う。インターネット上では、逆写真詐欺として有名な喫茶店だ。
こんな茹だるような――むしろサウナに放り込まれたような暑さだ。大きめのかき氷をシェアするのも悪くはない。
からんからんと扉を開けた瞬間、カウベルが鳴る。海の向こうから来たと思われる女性店員が空いてる席にどうぞ、と訛りのある日本語で案内する。
窓際ではなく、それでいてエアコンの風が直接当たらない位置にある空いている席に座ると、すぐにおしぼりとお冷の入ったグラスが並べられる。決まりましたらどうぞ、と去っていく店員をよそに、二人は向かい合わせに座り、期間限定と銘打たれたメニュー表を見る。
「クラフトコーラのかき氷だって」
「最近、よく見ますね。クラフトコーラ」
「まあおいしいしね。これのレギュラーサイズを二人でシェアしましょ」
「そうですね。飲み物はどうしましょうか」
「あたしはメロンソーダにするわ……あんたは?」
「アイスコーヒーを。かき氷ですが、追加料金でソフトクリームをつけられるそうですが、どうしますか」
「んん……ソフトクリームの気分じゃないからパス」
「わかりました」
近くを歩いていた店員を呼び止め、千種川は注文をする。復唱してキッチンに向かう店員を見ることもなく、千種川はおしぼりの袋を破ると、丁寧に手を拭いて四つに折る。
髪にこもった熱をはらすようにぱたぱたと首元に風を送っていた優は、あんたの星にもこんな暑い季節になる場所はあるわけ、と尋ねる。
「ここまで暑くはなりませんね。周期ごとに気候変動させるコミュニティーでも所謂真夏日、までしか気温を上昇させないと聞いています。他のコミュニティーは基本的に季節は一年中秋に近いですから」
「あー、言ってたわね……過ごしやすい季節だって」
「はい。基本的に過ごしやすい季節です」
「こうも暑い日が続くと、そっちの惑星が魅力的に見えるわね……」
「僕もそう思います。先日、青木が故郷のほうが過ごしやすい、と愚痴をこぼしていましたね」
「青木さんが?」
あの人の惑星ってどんな星か知らないけど。
眉を寄せた優に、千種川は端的に説明すると砂漠地帯です、と返事をする。
「砂の惑星ですね。朝は暑く、夜は寒い。乾季と雨季があるのもよく似ています」
「へえ。あんたたちの惑星とはまた違う景色だ。ピラミッドとか、そういうのあるわけ?」
「いえ、ないですね」
「ああ、ないんだ」
「地球の砂漠地帯に近しい、というだけで地球ではないですから。ちなみに、豆類が非常に美味で特産です。我々もよく輸入して食していました」
「へえ。それは食べてみたいかも」
「頼んでみましょうか、分けてもらえないか。所持していないか、確認することはできますが」
「まじ? お願いしようかな」
千種川がスマートフォンを操作して青木に連絡をつけている間に、ウェイトレスが注文していたかき氷とメロンソーダ、アイスコーヒーを持ってくる。
目にも鮮やかな緑色と、コーラカラーに染まったかき氷。かき氷は普段見るものよりどん、と大きい。二人でシェアして食べることにして正解だったわ、と思いながら優はスプーンでかき氷を掬う。口に入れるときん、とよく冷えた氷が喉を通って体を少し冷やした……ような気がする。
連絡はしました。そう告げた千種川に、先にいただいているわよ、と優はかき氷を指で指し示す。構いませんよ、と言いながら、千種川もまたスプーンでかき氷をひとすくいするのだった。