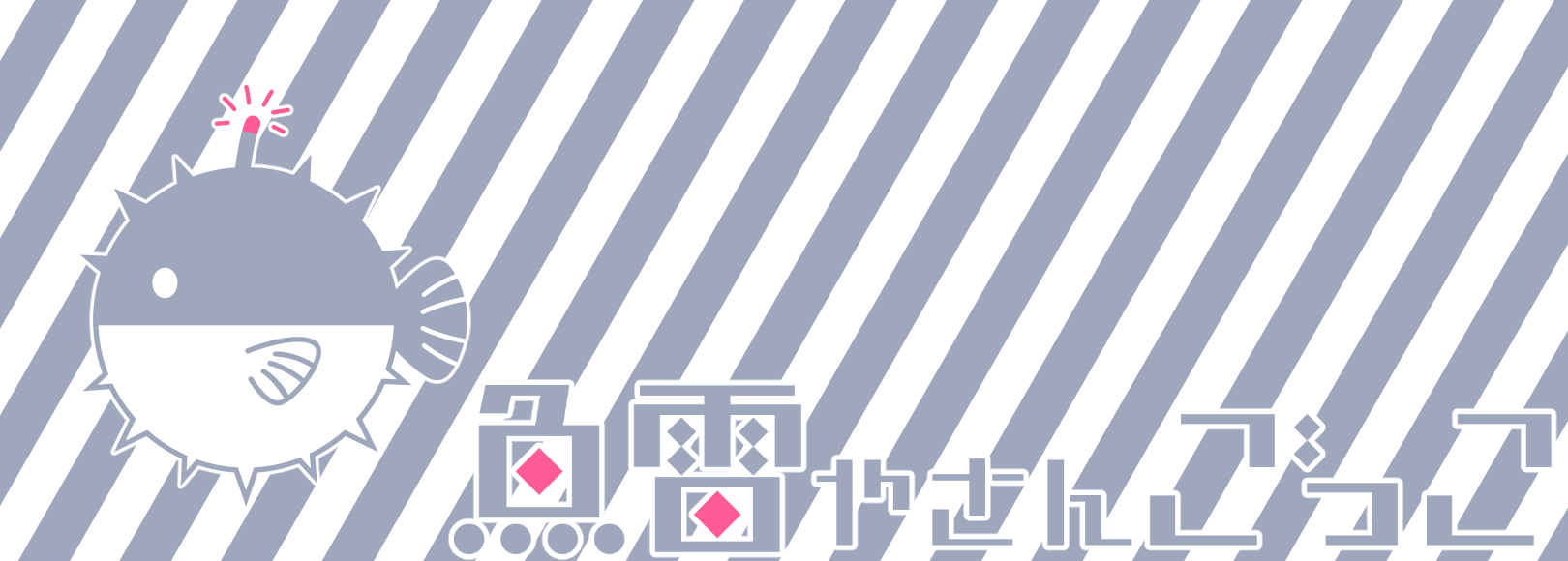二人は薄暗い街を歩いていた。無音、ガソリン車の匂いすらしない街を街灯が照らしている。アスファルトを照らす中、優は思い出したように口を開く。
「……あのさ」
「なんでしょうか」
「これ、さっきから同じ場所歩いてない?」
「そうですね。五度は同じ道を歩いています」
「……そういうどっかのゲームみたいなのは、あたしちょっと御免被りたいんだけど」
呆れたようにため息を吐き出す優に、ふむ、と千種川は腕を組む。くるり、とあたりを見渡した彼は、あれですね、と指を持ち上げる。白く、細い指を持ち上げた彼の指し示す先を見た彼女は、なにあれ、と興味深そうに尋ねる。
二人が近寄って見ると、そこにあったのは蒼白く輝く小さな結晶だった。コンクリートブロックの塀に埋もれるように生えているそれを、優がしゃがみ込んでつまみ上げようとすると、その結晶は彼女の指先をすり抜ける。おや、と思いながら優は再び手を伸ばすが、何度手を伸ばしても指先に硬質そうなそれの感覚を得ることはない。
なにこれ、と優が口を開けば、結節点の結晶ですね、と千種川は知ったようにしゃがみ込んでそれを見る。指先程度の大きさのそれは、薄く発光しながら二人の視線を受けている。
「結節点の結晶?」
「端的に言えば、怪奇現象の源、でしょうか」
「これがこのホラーゲームみたいなループを引き起こしてるって言うんだ?」
「そういうことです。信じがたいとは思いますが……」
「……まあ、はい信じますとは言えないけどさ。触っても触れた感覚がないんだから、信じざるを得ないって言うか……」
「これを潰せばここから出られるでしょう。結節点の結晶に関しては、日を変えて説明させていただきます」
それだけ言うと、彼はジャケットの内側に手を入れるとベージュ色の手袋を身につける。優が先ほどまで触ろうとしていた結晶に手を伸ばした彼は、そのままいともたやすく結晶をコンクリートブロックの塀から剥ぎ取る。コンクリートブロックの塀からもぎ取られた結晶は、彼の指先でつままれたままさらり、と崩れていく。
砂糖菓子が舌先で溶けていくように崩れていくそれと同時に、薄暗い街が空高くから静かに崩れていく。まるでドームのように、結晶を中心に覆われていた何かが溶けていく。瞬きをする暇も無く薄暗い街に戻る。しかし、先ほどまでの無音とは違い、遠くからは家庭の音が聞こえ、嗅ぎ慣れたガソリン車の匂いもする。
「……なんだったの、今の」
「僕も分かりません。ただ、対処方法が分かると言うだけで」
「ああ、あんたもそこまで分からないんだ」
「そうですね。我々の世界でも、先ほどのような結晶は存在しますし、時折今のように誘われることはあります。こちらで遭遇したのは初めてですが……」
「あたしだってはじめてよ。あんたといると、初めてのことに出会うのが多くて退屈しないわね、本当」
「それはなによりです。しかし、我々の星のような硬度は誇っていないようで残念です」
もう少し硬度があれば、持ち帰って研究も出来たのですが。
残念そうに呟く彼に、また手にできるかも知れないでしょ、と優は興味なさそうに呟く。手元のiPhoneを見れば、時刻はそれほど経っていないようで、少し前に見た――五回同じ道を歩く前の時間とほとんど変わっていなかった。そういうところもゲーム仕様なんだ、と言葉に出さずに優が思っていると、使い古しでよければ持ち歩いてください、と千種川が先ほど彼が付けていた手袋を差し出している。
それを受けとると、手袋は少しサイズを変えるようにもぞもぞとひとりでに動く。さすがにひとりでに動く手袋など初めて見た優は、ぎょっとしたように手袋をまじまじと見る。しばらくもしないうちに、手袋は少しばかり小さくなって動きを止める。
「……なに、いまの……」
「貴方の手の大きさに合わせたのでしょう。驚くほどのことでもないかと」
「いや、驚くわよ……で、これもらっていいの?」
「ええ。先ほどのように閉じ込められた際に役に立つでしょう」
閉じ込められるような現象が次も起きるとは限らないのですが、念のために持ち歩くことは選択肢にいれても良いかと。
そう言った彼は、自分の分はまた申請すればいいので、と何でも無いように告げる。ありふれたベージュ色の革のような素材で出来た手袋を見ながら、それじゃあ、と優は受け取る。試しに身につけてみれば、随分前から使っていたかのようにしっくりくる。
結節点の結晶については日を改めてお伝えします、とだけ告げると彼は優を大通りのほうへ連れて行く。最寄りの駅まで歩きながら、優は手袋の素材は革で合っているのかと尋ねる。革の染料に特殊な素材を利用しているが、至って普通の手袋だと千種川は返事をするのだった。