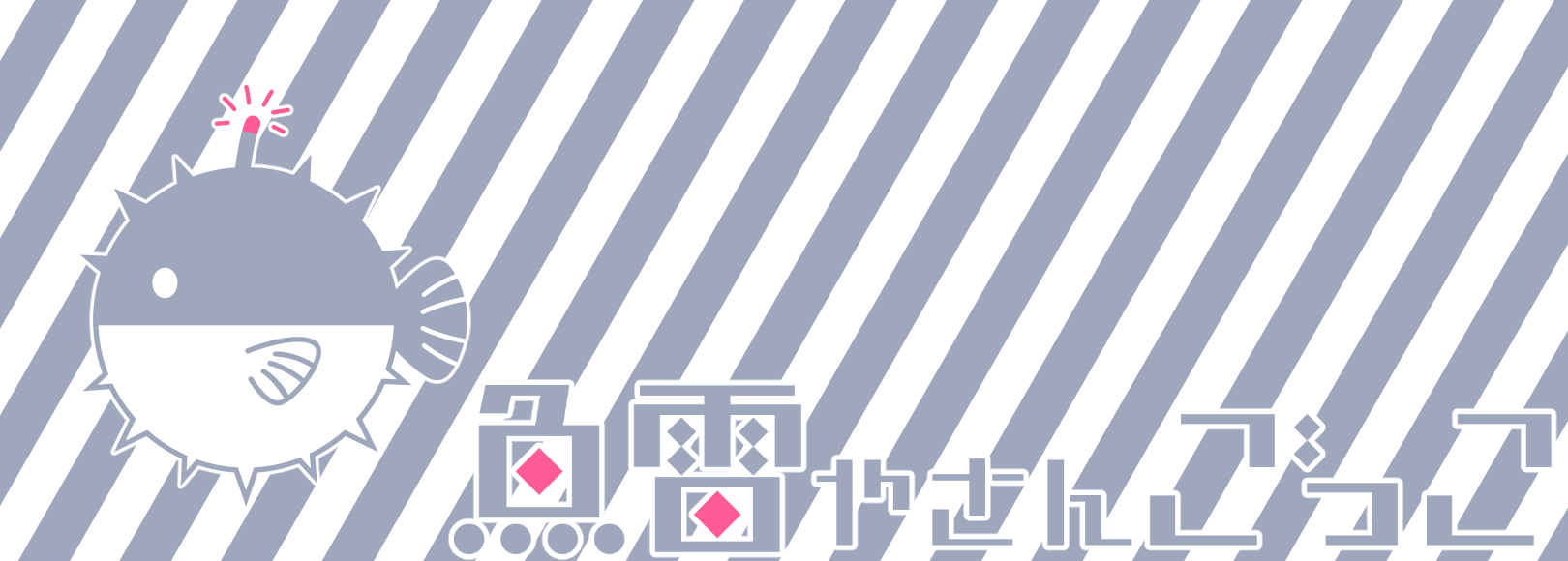その展覧会はいわゆる「用途不明のもの」を収集したものだった。それは雑多に収集された、古今東西の摩訶不思議なものの展覧会だった。
優はその展覧会に千種川に連れられてきたのだが、どういう理由があって彼がここに彼女を連れてきたのかがわからないままだった。まあ、理解できない事自体はいつものことであるから、大した問題ではないのだけれども。誘ってきた本人は数々の用途不明なものを一瞥しては、次の用途不明なものに向かっていく。作者が判明しているものの用途不明品に興味はないらしく、足早に歩いていく彼の後ろを優はついて歩く。
人のいない展覧会場を歩きながら、千種川は一つの用途不明品の前で足を止める。優はそれを一瞥して、きれいだと思う。作者不明だというそれは、ガラス細工の筒だった。それは薄いグリーンとブルーの混ざった色合いで、展示物を照らしているライトの明かりを反射させている。
「こちらです」
「ほかのよりはまあ、きれいな筒だとは思うけど……それがどうしたっていうのよ」
「これはガラスに近い性質を持つ素材で作られたものです」
「ガラスに近い? ガラスじゃないんだ」
「はい。ガラスに近いだけであって、ガラスではありません。我々の母星にある素材でもありません。検索はかけていませんが、他の惑星では近しい素材や同質のものがあるかもしれませんので、断定はいたしませんが」
「へえ……まあ、とにかく、普通のものじゃない、っていうことは確かなんだ」
「はい。そして、これに関しては特異な性質が観測されています」
学術員であるメンバーが検査にかけて判明したものです。
そう前置きした千種川は、優にスクエア型のリュックサックの中に入れていたクリアーファイルをとりだす。それには優が見たこともない言語で書かれた書類だった。コンピュータかなにかで色彩調整された画像がいくつかついているが、それが何を指しているのかも皆目さっぱりである。
なにこれ、と優が千種川の持つ書類を指差すと、これはあの筒を各種検査した結果になります、と返事が戻ってくる。
「かいつまんで説明しますと、あの筒には結節点の結晶に近い性質が観測されました」
「え、じゃあ、あの筒ってただのきれいな筒じゃなくて、前みたいなループする世界に引っ張られたりするかもしれない、ってわけ?」
「いえ、人為的に操作ができるようにされていました。ただ、その操作方法はわからずじまい……すくなくとも、あの筒そのものには人を害する機能を有していないだろう、ということでこうして博覧会に出すことが許可されました」
「ああ……なるほど……まあ、たしかに安全じゃなかったら、多くの人が来るだろう場所にむざむざ展示なんてしないわよねえ……」
「そういうことです」
まじまじと優はきらきらと光る筒を見る。それはiPhoneの最新のProモデルと変わらない大きさで、よく見れば両端に透明なガラスがかぶさっていて、筒に蓋をしている。筒の中央付近は握りやすそうに凹まされている。蓋代わりの透明なガラスは、取り外せそうな仕組みはないように見える。ガラスの仕切板越しに見ているから、本当は小さく取り外せる仕組みがついているのかもしれないが。
中央にライトでも仕込めれば、ちょっとした間接照明にでもなりそうだな、と優は思う。そしてそれは案外――彼女が思っていることは正解だったりする。
優はもちろん、千種川も知らないことだったが、こことは鏡合わせにある世界では、そのガラス製の筒は一部の上流階級と呼ばれる階層の人々が、自宅の寝室に置いているものだった。結節点の結晶が生まれる要素を集約して、光量を調整して部屋を照らすためのものだった。ガラス製の筒で作られているのは、部屋にさまざまな色をいれるためである。
――もっとも、優も千種川もそんな鏡合わせの向こう側の世界の事など知らないものだから、ただのガラス製の筒でしかないのだけれども。
「あなたはあれが何のために作られたものだと思いますか」
「あたし? あれは……んー……間接照明かな。中に明かりがあったらきれいだと思うんだよね」
「なるほど。筒の中に何らかの手段で光をいれると。あの筒の両端に説尾腐れているガラス蓋は取り外せないようになっていましたが……」
「そこはほら、結節点の結晶みたいな性質でどうにか? 人為的に操作できるんだったら、いいかんじにこう……」
「そうかもしれませんね。その可能性は大いにあります」
そううなずいた千種川は、資料をリュックサックにしまう。リュックサックを背負い直した彼は、他にもあのような品がこの展覧会にはあります、と他のものがあることを示唆すれば、優は次はどんなものなわけ、とどこか楽しそうな口調で続きを促す。作者不明の用途不明品という、普段ならば興味もないものが未知のものであるという側面を見てしまったからか、優は千種川を眺めるだけの態度から積極的に関わり始める。
彼女の態度が受動的なものから能動的なものになったものだから、千種川も満足げにうなずくと、こちらです、と次の用途不明品に足を向けるのだった。